
唎酒師(きき酒師)とは?試験内容や合格率、難易度を解説
※当メディアの記事で紹介している一部商品にはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトなどのアフィリエイトプログラムが含まれています。 アフィリエイト経由での購入の一部は当メディアの運営等に充てられます。
日本酒の資格に唎酒師(きき酒師)というものがあります。
お酒が好きな人はよく耳にする資格ですが、詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は唎酒師(きき酒師)の概要や試験内容、難易度などを解説します。
日本酒の資格を取得しようと思っている方や、日本酒好きの方はぜひ参考にしてみてください。
目次
唎酒師(きき酒師)とは?

唎酒師とはワインでいうソムリエのような資格で、飲み方や料理、季節などを総合的にアドバイスできる日本酒の資格です。日本酒の製造方法だけでなく歴史や文化についても精通しています。
本来は酒蔵で品質を確かめる検査業務のためにできた資格ですが、現在では居酒屋やホテル、酒屋などさまざまな場所で活用されています。
また唎酒師を受験者は、飲食業や小売業で働く人がほとんどで、日本酒に関わる業務に就いている人の割合が多いです。その他には、趣味で日本酒の知見を深めたいという人が取得をしています。
これからは趣味や教養として唎酒師を取得する人が増えてくると予測されています。「日本酒に興味があるだけで受験できるの?」「日本酒の仕事をしていない」という人でも受験ができますので、気軽に申し込みをしてみてください。
▼おすすめ記事
転売や偽装!日本酒にまつわる事件まとめ
唎酒師(きき酒師)の取得方法は3つ

唎酒師になるには日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会(SSI)の認定試験の受験が必要です。
取得方法は「通信プログラム」「2日間集中プログラム」「受験プログラム」の3つが用意されています。
通信プログラム
通信プログラムは、学習から受験まで全て自宅で行えるプログラムです。
自宅に教材が届き、テキストや動画で学習を進め、課題をクリアしていきます。その課題を3ヶ月で3回提出し、課題が合格基準に達していれば唎酒師の資格が与えられる仕組みです。
また資格取得後は無料セミナーなどがあり、さらに知見を深めていくことができます。全て自宅で行えることから、忙しい人や地方にいる人に人気のプログラムです。
2日間集中プログラム
2日間集中プログラムは事前学習を経て当日会場入りし、2日間の講義を受けるというものです。2日目には試験があり、合格をすると唎酒師の資格がもらえます。
また不合格者には補講や再試験が用意されていますので、一発勝負のプレッシャーに押し潰されることもありません。短期間で取得したい人や実際にテイスティングしてみたい人におすすめのプログラムです。
受験プログラム
受験プログラムは3つに分かれており、自宅で勉強をして合格を目指す「在宅コース」、会場で1日集中をして合格を目指す「1日通学コース」、夜間4回の講義で合格を目指す「夜間通学コース」があります。
会場は東京や大阪だけでなく、全国の主要都市でも開催しており、土日・平日どちらも対応しています。会場では実際に試飲ができるので、より深い学びができるのが魅力のひとつです。
どんな科目を勉強するの?
唎酒師になるためには以下の科目を学習する必要があります。
| もてなしの基 | おもてなしの知識や技能 |
| 食品・飲料の基礎知識 | 飲料の分類や特性、発酵、管理方法など |
| 食品・飲料の文化 | 食品や飲料の歴史、世界と日本の食文化 |
| マネジメント | 飲食やサービス業のセールスプロモーション |
| 日本酒の原料 | 米や水、麹など原料について |
| 日本酒の製造方法 | 精米から搾、瓶詰めまで全工程について |
| 日本酒のラベル表示 | 日本酒のラベル表記 |
| 日本酒の歴史 | 日本酒の歴史について |
| 日本酒のテイスティング | 日本酒の分類や提供方法をふまえたテイスティング |
| 日本酒のサービス | 提供方法について |
| 日本酒のセールスプロモーション | プロモーション例で学習 |
このように勉強する項目は日本酒だけでなく、飲料全般から歴史まで多岐に渡ります。
▼関連記事
日本酒の種類と、種類ごとのおすすめの飲み方を徹底解説
唎酒師(きき酒師)の試験内容や合格率、受験料

続いて唎酒師の試験内容に就いて解説をします。
受験資格
20歳以上であれば誰でも受験できます。
試験内容
通信講座をのぞき、会場試験では四次試験まで段階を踏むことになります。
| 一次試験 | 筆記試験 | 酒類や飲料全般の基礎知識 |
| 二次試験 | 日本酒の基礎知識と提案方法 | |
| 三次試験 | テイスティング | 2種類の日本酒をテイスティングし品質をチェック |
| 四次試験 | 筆記試験 | 日本酒の季節別の提案やサービス |
通信プログラムは課題の提出だけで合格できますが、会場で受験をする人は上記のステップをクリアしなければなりません。ただし合格率は高く、補講や再試験も用意されているので心配する必要はないでしょう。
合格率
ほぼ確実に合格できる仕組みが整っているため、合格率は80%前後と言われています。
受験料
受験料および登録料は以下の通りです。
・受験料:55,000円
・認定登録料:25,000円
・入学金:19,000円
・年会費:15,900円
受験料の他に登録料や年会費がかかります。思った以上に費用がかさむので、余裕を持って受験申し込みをしてください。
▼関連記事
日本酒の基礎知識!にごり酒の味わいや飲み方について紹介
唎酒師(きき酒師)以外にも日本酒の資格はある?

日本酒に関する資格は唎酒師だけではありません。気軽な資格から難易度が高いものまでさまざまです。
そこで日本酒に関する資格をまとめてみました。
日本酒検定
日本酒検定は日本酒を広く知って楽しんでもらうための資格です。1級から3級まであり、20歳以上であれば誰でも受験できます。
また準1級になると上位資格である「酒匠認定者」や「日本酒学講師」の受験資格がもらえます。初心者だけでなく難関資格を目指す人にもおすすめの資格です。
国際唎酒師
国際唎酒師は、唎酒師と内容は変わらないものの、試験は全て外国語で行われる認定資格。海外で活躍をしたい人やインバウンド対応をしたい人におすすめの資格です。
酒匠(さかしょう)
酒匠は唎酒師の上位資格で難易度も一気に上がります。日本酒だけでなく焼酎の知識も問われ、講習会では200種類以上の日本酒をテイスティングしなければなりません。日本酒に深く関わる仕事をしたい人におすすめの資格です。
SSI研究室専属テイスター
SSI研究室専属テイスターとは、酒匠の中から選抜されたテイスティングの専門家です。唎酒師と酒匠のトップ0.2%しか辿り着けず、日本でも100名以下しかいないスペシャリスト。難関資格として有名で、優秀な酒匠でも簡単に落ちてしまうそうです。
日本酒ナビゲーター
日本酒ナビゲーターは日本酒の魅力を知ってもらうための資格です。日本酒学講師のセミナーに参加すれば認定され、唎酒師よりも気軽に取得できます。日本酒を楽しく学びたいという人におすすめです。
酒造技能士
酒造技能士は他の資格とは違い、日本酒を製造するための国家資格です。酒造メーカーや酒蔵で日本酒を造る人が取得をしています。実務経験などが必要なので、合格までは長い期間が必要です。
まとめ
今回は唎酒師(きき酒師)の概要や試験、難易度を紹介してきました。
自分のペースで学べるプログラムが充実しているため、挑戦してみようと思った方もいるのではないでしょうか?
また日本酒検定や日本酒ナビゲーターなど、もっと気軽に学べる資格もあります。自分のキャリアプランや趣味に合わせて、資格を取得してみてください。
| ■この記事を読んだ方におすすめの記事 | |
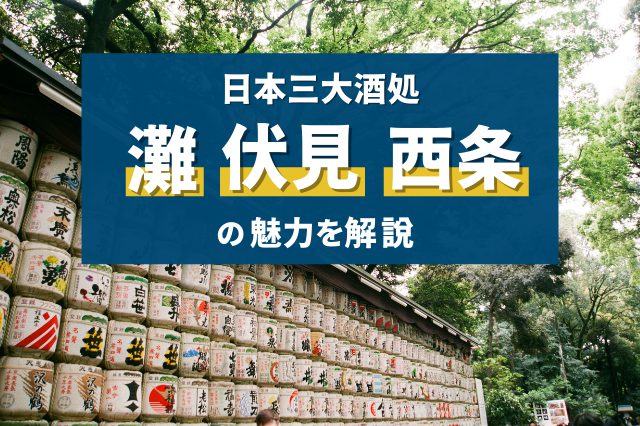 |
広島・西条の酒蔵7つを巡ってみよう!1日で回れる日本三大酒処 |
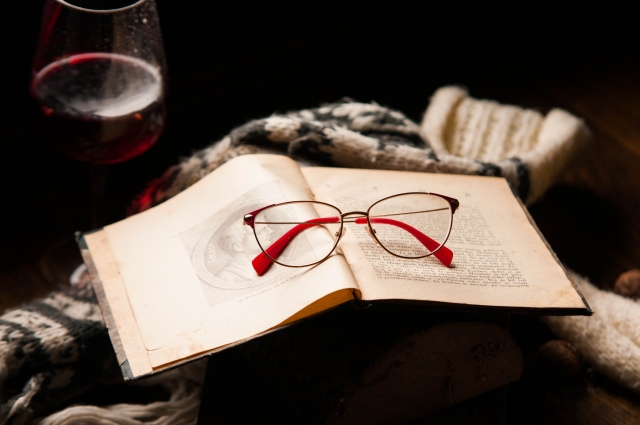 |
お酒好き必見!お酒をテーマにした人気漫画を一挙紹介!! |
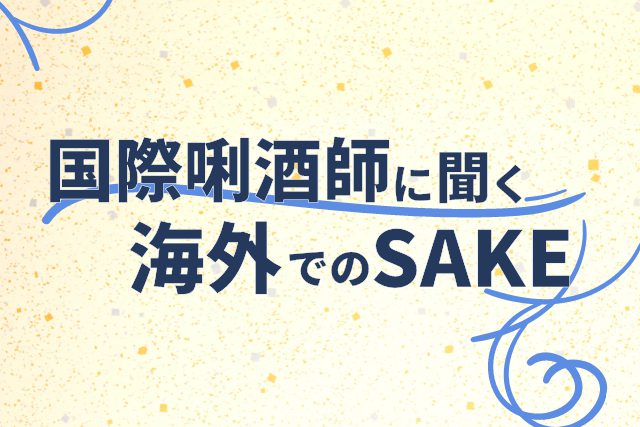 |
酔うために日本酒!? 国際唎(きき)酒師に海外での「SAKE/サケ」について聞いてみた! |








