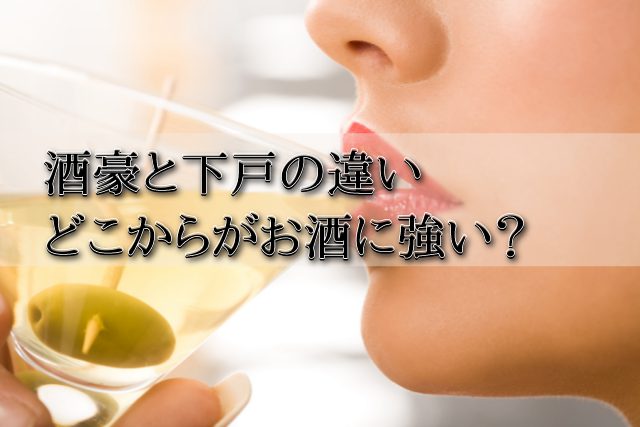
「酒豪」と「下戸」の違いは?どこからがお酒に強いのかを解説
※当メディアの記事で紹介している一部商品にはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトなどのアフィリエイトプログラムが含まれています。 アフィリエイト経由での購入の一部は当メディアの運営等に充てられます。
お酒の強さを表す言葉に「酒豪」と「下戸(げこ)」があります。
しかし、どれだけ飲んだら酒豪なのか、どこからが下戸なのか曖昧な人も多いのではないでしょうか。
自分は酒豪だと思っていても、世間から見るとそうでないかもしれません。
そこで今回は、酒豪と下戸の違いや、お酒の強いについて解説します。
お酒の強さについて知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
目次 [非表示]
酒豪と下戸とは?

それでは酒豪と下戸の特徴をみていきましょう。
酒豪とは
酒豪(しゅごう)とは酒(アルコール)を大量に飲める人を指します。
日本では「お酒をいくら飲んでも酔っ払わない人」「体調が変わらず大量に飲める人」を酒豪と呼びます。
またお酒を飲む人を「左利き」「左党」と呼ぶことも。これは江戸時代に大工さんが右手に槌、左手にノミを持っていたのが由来です。右手を「槌手」、左手を「ノミ手」と呼び、それが「飲み手」になったとされています。
そして反対の意味で、お酒が飲めない人を「右党」と呼ぶようになりました。
その他にも、いくらお酒を飲んでも満たされない「笊(ざる)」や、飲む量が多い人を蛇の丸呑みに例えて「うわばみ」、階級制度の名残で「上戸」、和製英語の「ドロンケン」など、さまざまな呼び方があります。
ちなみに英語圏で酒飲みを表すときは「heavy drinker」や「binge drinker」が使われています。
下戸とは
下戸(げこ)とは「全くお酒を飲めない人」、もしくは「少量しか飲めない人」を指します。
一般的に、体質的にお酒を受け付けない人を下戸と呼ぶようです。
下戸の語源には2つの説が存在します。
一つ目は江戸時代に使われていた言葉を元にした説です。
江戸時代、大宝律令の名残から最も位の高い人から大戸、上戸、中戸、下戸と呼ばれていました。そして婚礼の際に、階級毎に上戸は八瓶(はちへい)、下戸はニ瓶(にへい)とお酒の提供される量が決められていたと随書「塩尻」で伝えられています。この制度に由来して、お酒を飲む量が少ない人を下戸と呼ぶようになったという説です。
二つ目は中国を発祥とする説です。
秦の時代、万里の長城には門番がついていました。万里の長城には、寒さの厳しい山上の門「上戸」、人の往来が多い門「下戸」がありました。
そして兵士の体を癒すために、上戸の門番には体が温まる「お酒」、下戸の門番には疲れを癒す「甘いもの」が配給されたそうです。そのため、お酒を飲める人は上戸、飲めない人は下戸と呼ぶようになったという説です。
下戸の人はこういった豆知識を覚えておくと、飲み会の場で盛り上がるかもしれませんよ。
お酒の強い人、弱い人の基準はどのくらい?
どのくらいの量を飲めば「酒豪」と呼ばれるのか?いわゆるお酒に強い人の基準はどの程度なのか、気になりますよね。
お酒に強くなりたい人の情報サイト「ノメルヨ」が21~64歳の男女50名に「ビール(中ジョッキ500ml)をどの程度飲む人が酒豪と呼ばれると思うか」をアンケート調査したところ、
・10杯以上:15票
・5杯:10票
・4杯:7票
・7杯:7票
・6杯:5票
・8杯:4票
・3杯:2票
このような結果となりました。
多くの人は中ジョッキ10杯以上、もしくは5杯飲む人をお酒に強い「酒豪」と呼ぶ傾向にあるようです。反対に全く飲めない人や、2~3杯で飲めなくなる人は「下戸」というイメージになりそうですね。
またアルコール純量で考えると一般的な日本の中ジョッキビール1杯あたりのアルコール純量は20gほどといわれています。つまり、5杯換算のアルコール純量100gから、もしくは10杯換算の200g以上からが酒豪と言えそうです。
ビール以外のお酒であてはめて中ジョッキビール5杯分程度換算すると以下のようになります。
・ウイスキー(40%):シングル(30ml)を8杯程度。240ml。
・焼酎(25%):ロック(80ml)を6杯程度。480ml。
・日本酒(15%):1合(180ml)を5合程度。900ml。
・ワイン(12%):グラス(120ml)を9杯程度。1080ml。
ワインでみると、ボトル1本半程度を飲んでいる計算ですね。そもそもビールでも2.5ℓ飲んでいますし、筆者的には恐ろしい量だなと。。。。
ただアンケートの通り、酒豪と判断するラインには個人差がかなりあるようなので、参考程度にしながら、健康的にお酒は楽しみましょう。
酒豪が多い都道府県は?
酒豪と下戸の違いについて紹介しましたが、地域差などはあるのでしょうか??
なんとなくOO県の人はお酒をよく飲んでいる!というイメージもあるかと思います。
全国の男女14万人を対象に調査した「ココロの体力測定2019」を、ダイヤモンドオンラインが独自に集計した「酒飲みが多い都道府県ランキング【完全版】」では、以下のような結果が出ていたの見ていきましょう。
このランキングを見ると、東北地方の飲酒率が高いことが分かります。
やはり寒い地域は、お酒を飲んで温まる習慣があったのかもしれませんね。
お酒が強い人はなぜ飲める?

お酒の強い人は、なぜ多くの量を飲めるのでしょうか。
そこでアルコールを大量に飲める理由を解説していきます。
遺伝子の違い
お酒の強さは体質や遺伝によって決まります。
アルコールは、体内で分解する過程でアセトアルデヒドという物質が発生します。アセトアルデヒドは、頭痛や吐き気を引き起こす有害な物質です。
このアセトアルデヒドは「ALDH2(アルデヒド脱水素酵素2)」によって分解されます。しかし日本人の約40%は「ALDH2」の活性が弱く、分解に時間がかかってしまうのです。
ALDH2の活性は、遺伝によって引き継がれるものです。そのため生まれた時からお酒の強さは決まっています。
お酒の分解に関わる遺伝子の調べ方は別の記事でもまとめているので、気になる方はチェックしてみてください。
関連記事:お酒に強い、弱いはどうやって決まるの?原因や調べ方を解説!
体重の違い
体重の重い人ほど、お酒に酔いにくいとされています。
なぜなら体重が重くなると、水分量や血液量が多くなるからです。
血中アルコール濃度が相対的に濃くなりにくいため、飲める量も多くなります。
逆に体重の軽い人は、血中アルコール濃度が高くなりがちで、酔いも回りやすいとされています。
性別の違い
一般的に男性より女性の方が、お酒に弱いといわれています。
なぜなら、女性は男性よりも肝臓が小さく、アルコールの分解に時間がかかるからです。
個人差はありますが、1時間で代謝できるアルコール量は男性約8g、女性約6gといわれています。女性は男性よりも血中アルコール濃度が高まりやすく、肝臓に負荷がかかりやすいのです。
年齢の違い

歳を取るとお酒に弱くなり、飲む量が減っていきます。
年齢が上がる毎に肝臓の機能も低下し、アルコールの分解速度が落ちるからです。また若い時よりも体内の水分量が減るため、血中アルコール濃度が上昇しやすいリスクもあります。
特に若い時、お酒を大量に飲んでいた人は注意が必要です。肝機能へのダメージも大きく、転倒や事故につながる可能性もあります。
お酒を長く楽しむためにも、自分の適量を知っておくことが大切です。
まとめ
今回は酒豪と下戸の違いや、お酒の強いについて解説してきました。
生ビール10杯、5ℓも飲んでいたら、確かにお酒を飲めれば強いです。しかし全く健康的ではありません。
お酒の強さで張り合うのではなく、お酒は楽しく、健康的に飲むようにしましょう。
本記事を参考に、お酒の強さについて考えてみてください。
| ■この記事を読んだ方におすすめの記事 | |
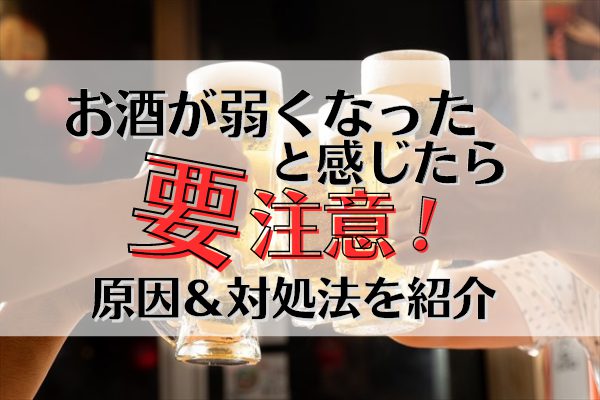 |
お酒が弱くなったと感じたら要注意!原因と対処法をまとめて紹介 |
 |
二日酔いに効く市販薬とは?選び方やおすすめを紹介 |
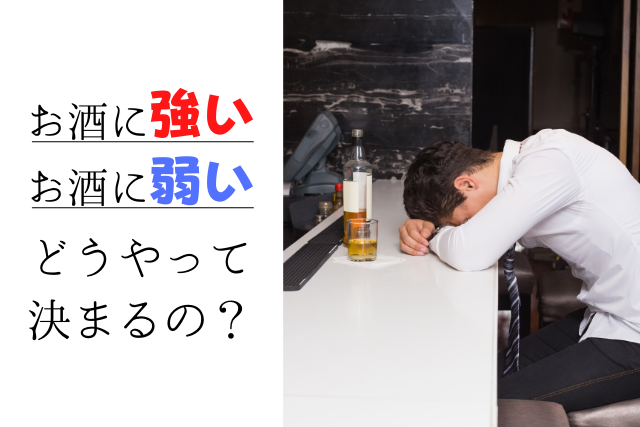 |
お酒に強い、弱いはどうやって決まるの?原因や調べ方を解説! |








